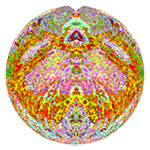近代における犯罪・雇用・差異
包摂主義とその急進派
「寛容の一九六〇年代」が到来すると、戦後の時代はひとつの頂点を迎えた。法的・政治的 な市民権が階級や年齢、人種、性別を越えて広まるにつれ、社会契約の範囲内で許容される 「正常」の定義も拡大していった。かつては逸脱とみなされていた行動、すなわち社会契約の 範囲外にあると定義されていた行動も、大幅に認められるようになった。それは、少年非行と 「被害者なき犯罪」[ 1965年アメリカの社会学者エドウィン・シャーが提唱した概念で、売春や麻藥・中絶などの違法行為や同性愛などの超越行動を指す ] という二つの領域でとく に顕著にみられた。一九六〇年代に初めて少年犯罪が増加したとき、多くの国の政府がしたことは、少年の正常な成長過程で起こる失敗としての少年犯罪と、少数ではあるが深刻な適応障 書に悩む少年の犯罪を区別することであった。一九六八年にイギリスで公刊された「少年犯罪 白書 事件のなかの子どもたち」は、その区別をよく示している。
法に抵触する不適切な行動をまったくしないで育つ子どもは、少数しかいないだろう。そのような行動は、子どもの正常な成長過程の範囲内にあるもので、たいした問題ではない。 しかし、なかには不十分な家族環境や社会環境のせいで起こった行動や、学校生活や学校以外の生活にうんざりして起こした行動、適応障害や未成熟を示す行動 、さらに生活が逸脱したり崩れていたり、異常であったりして起こる行動もある 。
要するに、ほとんどの少年非行は正常な行動であり、それは語のいかなる意味においても 「犯罪」ではないということである。さらに、より「深刻」な少数の事件でさえ、実際は犯罪
とはみなされなかった。というのも、それは環境的要因から生じたものだからである。少年非
行は主体的な意志にもとづくものではなく、外部の要因に決定されたものであった。つまり、
犯罪は、人間の悪意が犯罪を生むという古典的な枠組みではなく、外部要因の作用と反作用の
メカニズムから捉える実証主義の枠組みによって理解されるべきものであった。したがって、
少年非行とは正常な行為であるか、あるいは何かが欠落したことから生じる行為であった――
いいかえれば、それは正常、ないし正常性における一種の欠乏とみなされたのである。
昔の常識でいえば、およそあらゆる国でもっとも法律違反をおこなっているのは若者である。 不法侵入や路上強盗、窃盗、公共の場での乱闘などがもっとも頻繁にみられるのは、若者世代
である。少年非行を「犯罪」というカテゴリーから救い出し、「正常な若者の行動」(われわれ も 若い頃はそうだった)と「少数の適応障害による行動」(奴らはわれわれのようには成長し
なかった)のどちらかに当てはめるというこのやり方こそ、「包摂」そのものである。そして、この後者の「深刻な」逸脱について、それは悪意からではなく社会的訓練が受けられなかった ために起こったと解釈すれば、自由主義的な社会契約説に昔からつきまとっていた都合の悪い 亡霊——「この逸脱は階級間の不平等の産物かもしれない」という可能性——を追い払うこと ができる。ペッカリーアがよく理解していたように、「合理的な犯罪者」というのは、社会的 な適応技術をもたないために私たちと区別された人々のことではなく、財産と収入にかんする 既存の制度が根本的に不平等であることを少しでも理解したために私たちと区別された人々の ことである。そうした人々による犯罪は、たんなる一般的規範からの逸脱ではなく、階級間格 差から生じたものである。またジョン・ピッツが指摘するように、包摂主義的な政策は「若者 にかんする司法制度を晩犯罪化するとともに盼政治化する試み」でもあった [1997, p.255 強調は原著 書による)。かりにそのような政策が実現していたら、これまで当然のように犯罪とみなされて いた行為の大部分が、刑事司法制度の管轄から除外されてしまったことだろう。しかし実際に は、こうした改革にたいする根強い政治的抵抗があった。そのために、一九六九年の「少年犯 罪法」は、現在からみてもラディカルな側面があったのだが、大幅な譲歩を迫られることに
なった。ボトムズとスティーヴンソンによれば、これらの政策は「イギリスの成文 法ではかつてないほど福祉国家の理念が刑事司法に適用された」 結果であった [1992.26]。こ れを補足するさまざまな政策が立案されたが、ヨーロッパのいくつかの国々(たとえばス ウェーデンやオランダ)では他に例をみないほど福祉国家の力が強まっていた。実際、犯罪の脱政治化は「犯罪加害者を政治的対象とみなすことを止め、科学あるいは専門家の対象とみな
す」(1150) 動きとなり、その流れは一九八○年代までに驚くほど進展した。ジョン・ピッ
ツの指摘によれば、イタリアのボローニャを囲むエミリア・ロマーニャ州では、同州の一五〇 ○万人の人口のうち、一九八七年に保護観察処分に付された未成年者はたった二人しかいな かった。その十年前には四〇〇人の少年が拘禁されたというのに、である。 いうまでもなく、かつての少年犯罪はもっと排除的な観点から捉えられていた。一世紀前の 施策と比較してみれば、右に述べた脱政治化の動きがどれほど極端なものであるかが容易にみ てとれる。ヴィクトリア朝時代には、社会的差異とつきあっていくのに、それほどの困難はな かった。というのも、人々はかんたんに悪事に手を染めたからである。ヘンリー・メイヒュー [11] が描いた浮浪児は、ブルームスバリーの片隅やケンジントンの北部でかれらを目にして
いたヴィクトリア朝の人々にとって、明らかに自分たちとは異質な存在であった。ヴィクトリ
ア朝の人々は、スコット・フィッツジェラルド(後述) のように「貧しい連中は、われわれと 似ていないというより、われわれとは異質な連中だ」と語ったことだろう。実際、ジュディ ス・ウォーコヴィッツが的確に述べているように、ブースやメイヒュー、グリーンウッドなど のヴィクトリア朝時代の都市生活の観察者は、社会的差異を描くために、わざわざ大冒険に出 かけていった。「都市を冒険した文学者たちは、まるで人類学者のように特権的なまなざしで、 貧民たちを自分たちと異なる人種として、あるいは国家共同体の外側に位置するものとして描いた」(1919)。さらに、「アースとその仲間たちは、〈理解不能なもの)を〈理解可能なもの) にするために、都市のスラム社会にラマルクやスペンサーの進化論を適用した。ブースたちは、 性別役割や性行動の逸脱を、生物学的な退廃のしるしと解釈した」 [2]。漫画でも博愛団 体の冊子でも、とりわけ都市に住むユダヤ人とアイルランド人が描かれるときには、社会的差 異の底流にある人種的差異が強調され、さらにダーウィンの著作に由来する「先祖返り」の概 念が多用された(ラマルクやスペンサーの概念が多用されたのはいうまでもない)。こうした ことすべては、アンダークラスの文化的差異や人種的差異が強調される、二〇世紀後半の社会 的差異の世界を予告しているようにみえる――しかし、どうやら話を進めすぎたようなので、
この点については後回しにしよう。
ここですぐに私たちの関心を引くのは、逸脱を狭く定義し、最大限の寛容をめざす一九六〇 年代のラディカルな包摂主義と、それ以前の時代の排除主義との対比についてである。そこか ら、一九六○年代の包摂主義の根底にある二元論的な特徴が示される。すなわちこの包扱主義 は、ほとんどの 「社会問題」を正常とみなし、残りのわずかな部分を病理とみなす、二元論的 な特徴をもっている。この特徴は「被害者なき犯罪」の領域にとりわけ顕著にみられる。ここ で
は、とくに麻薬と同性愛という二つの領域をかんたんに取りあげてみよう。 麻薬の合法化にかんする議論は、時代とともに変わってきた。かつて麻薬使用は、不道徳な 行動であり、異なる世界への欲求、ボヘミアン的な生き方、そして空想的な感受性の高揚と関連づけて捉えられがちであった。しかし、現在になると、麻薬使用は不適応の問題として捉え られるようになった。麻薬にたいするイメージが歴史的に変化したのである。かつて詩人の コールリッジや評論家のド・クィンシーはアヘン中毒であり、小説中の人物であるシャーロッ ク・ホームズもモルヒネ中毒であった。そうした肯定的なイメージも、現代になると「ひ弱な 超自我、依存的な自己、男性としてのアイデンティティが欠如した」 「たとえばChein, et al., 1964] <D イン中症者という情けないイメージに取って代わられた。つまり、麻薬中毒は社会的差異から 「欠如」へと変わってしまった。その重要な帰結として、かつてのヘロインは明らかに肯定的 で魅力をもつものであったが、それも文学で取りあげられなくなり、現在ではたんなる現実逃 避の手段として求められるにすぎないものと捉えられるようになった。 また一九六〇年代のラディカルな人々のあいだに起こったマリファナ合法化をめぐる論争が、
包摂主義的な意見に落ち着いたのも、ごく自然ななりゆきであった。マリファナ使用者は「わ れわれと同じ人間」であり、ただかれらはビールを飲む代わりにマリファナを吸っているにす ぎない、と主張されたのである。しかもマリファナを合法化すべしという議論のなかには、合 法化すれば正常なマリファナ使用者が反社会的な麻薬中毒者にならずにすむという議論まで含 まれていた(この議論については私自身にも責任がある) [Young, 1971参照)。この議論では、マリ ファナの使用と新しく生まれたボヘミアン文化の結びつき―——差異の文化というものがあると
したら、これもそのひとつである―——が完全に無視されている。実際は、この結びつきこそが当時のマリファナに反対するモラル・パニックを説明するものであった [Young, 1972)
「寛容の一九六〇年代」という神話があまりにも広まったおかげで、当時の制度改革がかな り制限されたものであったことがしばしば見落とされている [Greenwood and Young 1980]。成人男性と うしの同性愛の合法化をめぐる議論は、まさにそのことを示す格好の事例であろう。その議論 では、同性愛者の(さまざまな) ライフスタイルにはまったく言及されることなく、ただひた すら同性愛を精神障害として受け入れるかどうかをめぐって展開された。たとえば、イギリス 下院議会の「性犯罪法案」の第二読会の冒頭陳述で、同性愛の合法化論者であるレオ・エイブ スは、同性愛者は「男性の身体と女性の精神をもって成長した人々」 [Hanund, 19 December 1966, cal.1086] であると主張していた。こうして、正常/異常の二項対立が男性/女性の二項対立にす り替えられ、同性者の男性は不十分な男性、いわば名誉女性として扱われるようになった。そ れだけではなく、同性愛者が「 女性 」とみなされたことで、かれらは「正常」なカップルとし て安定した関係を築くことができるようになり、その結果、同性愛者のカップルはもはやパパ とママからなるカップルに比べてとくに危険なものではなくなった。しかし、そこでも取り残 された人々がいる。たとえば、肛門性交愛者は未成年者に危害を加えるとみなされ、合法化の議論から排除されていった。そうした人々は、法的介入の対象とされ続けたのである。同性愛
が議論されるなかでは、こうした病理学的な観点の是非が問われることもなければ、そこで用いられた二項対立の論理が問題とされることもなかった。
以上、包主義の言説が、あらゆる差異を「同じもの」か「欠如したもの」のどちらかに、 あるいは「正常なちの」か「異常なもの」のどちらかに還元してきたことをみてきた。「われ われと同じ人々」と「われわれがもつものをもたない連中」という二分法は、いかなる差異の 償跡も消去してしまう。こうしたことも、後期近代の排除型社会の到来によって、すべて変わ りはじめた。差異は追求すべき至高の価値となり、自由に認められ、受け入れられ、しばしば 誇張されるまでになった。排除主義の時代に問題となるのは、差異ではなく困難である。包摂 型社会は、多くの合意と少ない困難から構成された社会であった。合意はたえず維持されたが、 他方で差異は徹底的に取り除かれた。当時の包摂主義的な政策は、労働市場があらゆる人々を 取り込むことによって、また政治的・法的・経済的な市民権の着実な発展によって、そして物 買的な成功によって施行できるようになった。そして包摂主義の時代には、あらゆる世代の 人々の生活が向上し、人類史における最高水準にまで達した(第1章を参照)。
後期近代の変容
前章で私は、近代社会を土台から堀り崩し、変容させることになったいくつかの外的要因に ついて詳しく検討した。社会は多様化するにしたがい、さまざまな困難を抱えることになった。 価値観の多元化や、海外移民の流入、下位文化の多様化といった現象は、これまでの絶対的基準をちはや通用しないものにしてしまった。いまや、社会的困難はいたるところにあふれてい る。たとえばイングランドとウェールズでは、一九五五年から九五年のあいだに犯罪発生率は 一一・五倍になり、暴力事件は二〇倍にまで激増した。後期近代の道徳家が直面しているのは、 人々が多様化し同化困難な人々が急増したという問題である。もはや美徳は永遠に消え去って しまい、厳格な道徳は過去の遺物になりはてた。他方で犯罪は「正常」な出来事となり、一般 市民にとって日常生活の一部になりつつある。
このような劇的な変化のために、後期近代における寛容/不寛容の構造は、しだいに近代
世界のそれとは正反対のものになりつつある。多様性は容認されるようになり、ライフスタイ
ルの差異はむしろ賞賛されている。しかし他方で、同化困難な人々はますます許容されなく
なってきた。この変化は、レヴィ=ストロースの言葉でいえば「人間を飲み込む社会」から 「人間を吐き出す社会」への変化ということになる。一九七〇年代初期に多くの著作家がこの レヴィ=ストロースの比喩に魅了されたのは、そうした社会的背景があったためと思われる。 排除型社会は社会統制の新しい方法を開発する必要に迫られている。人々を飲み込ん、抱き
かかえる戦後の社会は変容し、現在は人々を排出し、分離し、排除する社会になった。たしか に、この変化はレヴィ=ストロースの二分法を思い起こさせるものであるが、実際に起こ 事態はそれほど単純ではない。というのも、実際は、後期近代は「飲み込む」側面とともに 「吐き出す」側面もそなえているからである。それは内部に多様性を取り込みながら、寛容性のさまざまな程度に応じて包摂と排除をおこなっているのである。さまざまな社会統制の制度 が変化したが、それは後期近代の社会システムが直面している問題にたいする応答としてであ る。それは、ますます多様化する世界にたいする、あるいは犯罪と社会病理が途方もなく拡大 した世界にたいする応答としてである。要するに、社会的差異と社会的困難がともに増加した ということである。ここで誰の目にも明らかと思われる事実を強調しておきたい。それは、あ る社会が直面しているさまざまな問題は、その社会がそれらの問題を解決する方法を大きく規 定する、という事実である。なぜこのようなことをあえて強調するかといえば、これら両者が 独立したものと考える人々が多いからである。たとえば警察や監獄、さまざまな犯罪防止制度 が、それらが解決すべき当の問題とは無関係に発展してきたと信じこんでいる人々がいる。さ らに言えば、犯罪や逸脱を規制する統制様式が、「正常」な行動を促すための統制方式とたい して違いはないと考える人々もいる。こうしてみると、これと同じような考え方は社会のあら ゆる領域に広がっていることに気づく。実際には、社会統制は警察のパトロールや刑務所だけ に限られるものではないのだ。
したがって排除の様式も、過去のそれとは異なり、現在のさまざまな現象に対応したものに なっている。とはいえ、それはスイッチのオンとオフを切り替えるように、包摂と排除を切り 替えるというものではない。つまり、人々を社会の内側にいる者と外側にいる者にきれいに分 削しているわけでもない。むしろ、それは社会のいたるところで機能する、選別のプロセスなのである。社会的排除は、富裕層の信用格づけにはじまり、投獄された囚人の危険度の評価に いたるまで、さまざまな段階がある。ここで評価されるのは「リスク」であり、その大きさは 保険統計的な観点から、すなわち計算と査定によって決められる。そのような社会のイメージ を述べるなら、それはインサイダーが中心にいてアウトサイダーが周縁に追いやられるという 同心円状のイメージではなく、地位に応じて人々が順番に並んだビーチのようなイメージであ ろう。ピーチの一番上では金持ち連中がさんさんと日が当たる場所でカクテルを味わっている が、一番下では貧民がいまにも海に溺れそうになって必死にもがいており、なかにはそのまま 死んでしまいそうな人々もいる。このビーチは上から下までなだらかにつながっているが、そ れでも大金持ちとアンダークラスのいる場所ははっきりと分けられており、人々が場所を移動 することはできなくなっている。
保険統計主義の出現
ヨーロッパの金融都市フランクフルトでは、多くの道路が忘却へとつながっている。 ゴミ箱の陰に隠れて麻薬を注射することもできるし、階段の踊り場でトリップすること もできる。ドイツの大銀行のガラス張りの本社ビルがひしめく通りには、国費でつくられ た快適な部屋があり、そこに入って鉢植えを見ながら、ヘロインを心ゆくまで樂しむことりできる。
ヨーロッパはいまやドラッグ革命の最前線にいる。チューリヒでは中毒者にヘロインの 処方箋が出され、市が援助する施設で注射してもらうことができる。麻薬中毒者が注射す るそばには市の職員が付き添い、医者が適切な投与量をコンピュータで管理している。オ ランダでは、来年の五月から、アムステルダムとロッテルダムの市当局が、中毒患者に試 験的にヘロインを提供する。そしてドイツの麻薬専門家は、ハンブルクやシュツットガル トのような大都市でもフランクフルトと同じ施策を実行するよう圧力をかけている。これ は――少なくとも今のところは――だれにでもヘロインをばらまいているわけではなく、 ハード・ドラッグの中毒者のために管理された環境を用意してやろうという施策である。 ドイツでは、かりにマリファナをめぐる議論が起こるとしても、せいぜいのところ運転中 のマリファナ服用を認めるかどうかが問題になる程度だろう。それにたいしてハード・ド ラッグの中毒は社会問題になっており、そのため右で述べたような施策が実行されること になったのである.……………。
市の老人連中はこうしたハード・ドラッグ対策に賛成している。なぜかといえば、理由 はいたってかんたんである。店主たちは、店の入口に麻薬中毒者が意識を失って寝ころん でいることにうんざりしている。都心部の住民たちは、麻薬を過剰に摂取した十代の若者 たちを町内の路上から追い払うため、民間警備会社に多額の金を支払うことを嫌がっている。そうしたわけで、堅実な市民たちはもはや礼節をかなぐりすて、不動産価格と営業利 益を守るために、政府が援助する「ヘロインルーム」政策を支持しているのである。
後期近代社会における社会統制の基調にあるもの、それは「保険統計主義」である。すでに みたように[第2章の抜2-2 (一一九頁)」、ここでは正義を追求することよりも被害を最小限にする ことが求められている。そして犯罪や逸脱の原因を探ったところで犯罪という社会問題は解決 しないとみなされている。保険統計主義の中心にあるのはリスク計算である。それは精度の高 い確率論的解析であり、そこで注意が向けられるのは問題の原因ではなく、その問題が起こる 蓋然性である。保険統計主義にとって重要なのは、正義ではなく、被害の最小化である。それ が目的とするのは、世界から犯罪をなくすことではなく、損傷を最小限にする効果的手段であ る。それが追求するのは、ユートピアをつくりだすことではなく、敵意に満ちたこの世界に塀 で囲まれた小さな楽園をできるだけ多くつくりだすことである。保険統計主義に反映されてい るのは、個人と社会の領域においてリスクが増加しているという事実である。犯罪は日常生活の一部になるくらいまで常態化した。犯罪者はいたるところに現われ、街の裏通りだけではな く、地位の高い人々のあいだにも現われるようになった。また犯罪 は、街の貧しい地域だけで
はなく、犯罪被害者を保護するはずのシェルターや犯罪者の更正施設でさえ発生するようになった。さらに犯罪は、見知らぬ人々と出会う公共空間だけではなく、夫と妻、親と子どもと いう家族関係の内側にまで入りこむようになった。ボーイスカウトの隊長や警察官、ヒッチハイカー、ベビーシッター、夫、恋人、義理の父や母、高齢者を介護する人々――これらの人物 が、すべて警戒され、疑われるようになった。あらゆる人物が警戒すべき「他者」となり、そ れは犯罪者やよそ者だけに限られなくなった。犯罪の原因はますます理解不能になり、どこで 犯罪が起こるか分からなくなった。これらのことから、犯罪への不安もますます強まっている。 そうした状況から、個人も社会制度も「どうしたら危険な人々のなかから安全な人々を選別す ることができるか」という問題に直面することになった。しかし、正確で確実な選別方法がな いために、結局は確率に頼って選別する以外に方法がない。
規範も多元的社会によって脅かされているもののひとつである。 る。多元的社会では複数の規範
が併存しており、なかにはどの集団にも重なるような規範もあるとはいえ、すべての集団に等 しく適用される規範は存在しない。さらに規範は時代とともに変わるだけではなく、個人の人 生の短い期間でも変わるものであり、また変わってきたものである。それはまぎれもない事実 である。したがって、もはや「何が正しくて何が誤りなのか」ということは問題にされなくなった。その代わり、「どれが破られそうな規範なのか」「実際に被害をもたらしそうなリスク 要因はどれか」といったことが問題にされるようになった。個人の責任を問題にすることは、 しだいに重要性を失っていったのである。たとえば、あなたがショッピング・モールの支配人か、あるいは家族を守ろうとする母親であったとして、ある人物に危害を加えられたとしよう。 そのとき、この人物が精神異常者であるか悪人であるか、規範を遵守する能力があるかないか などは、あなたにとってどうでもいい問題である。したがって「犯罪は自由意志にもとづく行 為なのか、それとも環境に決定された行為なのか」という区別は曖昧なだけではなく、無意味 ですらある。あなたにとっては事件を理解することよりか、事件を避けることのほうが重要な はずが――こうした理屈から、起こってしまった事件を道徳的に非難することよりも、事件が 起こらないようにリスクを最小にすることのほうが重要とされていった。
保険統計主義と「新刑罰学」
このような保険統計主義の言説は、とりわけマルコム・フィーリーとジョナサン・サイモン の独創的な「新しい刑罰学」 [1992] において巧みに指摘されているものである。ただしかれら の著作は、現象面の記述については目を見張るものがあるが、保険統計的な言説の起源を説明 する部分では、それを犯罪発生率の上昇と切り離して考えるという、よくある誤りを犯してい る。かれらは、合衆国では「過去一五年間に、収監者数は劇的に増加しているにもかかわらず、 同時期に記録された犯罪発生率はゆっくりとしか増加していない」 [ibid. p.450]と指摘している。
そしてその時期に合衆国において保険統計的な言説がどのように起こったのかを明確に記述している。 ている。しかし、かれらが与える一連の説明は、まったく皮相なものである。つまりかれらは、 保険統計的な言説が起こった原因は、経営システム理論が公共政策学や商学などの領域に与え た影響や、法学や経済学における最近の知的流行にあると説明する [Feeley and Simon, 1994)。
かれら はそのことを次のように要約している。「犯罪統制にかんする司法の保険統計主義が生じたの は、社会全般におけるテクノロジーの発展に原因が求められる」 [1994, p.185]。ここでは、犯罪 そのものが重要な要素であるとは考えられていない。つまり、刑事司法制度に加えられている 圧力と、その言説や実践における変化とのつながりが、まったく考慮されていないのである。 フィーリーとサイモンは、刑事司法制度にたいする外的圧力の存在を認めてはいるものの、そ れでも収監者数の増加こそが新しい刑罰学が生まれた「原因でもあり結果でもある」と主張している。
また、かれらは刑事司法制度における保険統計的な変化を、犯罪の増加と切り離して考察しているだけではない。さらにかれらは、保険統計主義を単純に統制機関の傾向にすぎないと考 えており、それが社会制度と人々の両方に普及した態度であるとは考えていない。こうした思 考上の欠陥は、ある側面では、「リスク」という概念の内容を検討しないまま放置したことに 由来しているが、さらにいえば、そのリスクが現実の変化なのか、それとも認識上あるいは現 象上の変化でしかないのかを明らかにせず、曖昧な態度でごまかしたことにも由来している。
保険統計主義が道徳的に中立であることは、きわめて重要な意味をもつ。というのも、それはジグムント・バウマンが無関心化と呼ぶ、ポスト近代的な感受性の一部をなすものだからで ある。無関心化とは「人間関係から道徳的な意味をはぎとり、道徳的評価を免除し、さらには 「道徳とは無関係なもの」にしようとする」態度のことをいう [1995, p.133]。ジョナサン・サイモ ンは、未来の保険統計主義社会のシナリオを次のように描いている。
生活の背後にめぐらされたセキュリティ・システムは、抑圧的で強制的なものになってい くだろう。さまざまな社会統制が、安全を確保し、社会的コストを引き下げるという名目 で、人々の労働や生活の仕方を支配するために導入されるだろう。そのような統制は、伝 統的な刑事司法における社会統制とはまったく異質なものになるはずである。ドラッグの統制がいい例であろう・・・八〇年代にドラッグが禁止されたのは、たんにドラッグが交通事故のリスクを上昇させ、生産性を下げると考えられたからにすぎない。
統制のシステムも同じように変化しつつある。近い将来、雇用の条件として尿検査が課されるようになり、それによって効果的にドラッグ使用を減らすことが可能になるだろう。 国家がドラッグを使用した個人を道徳的な目的で処罰するということはなくなるだろう。 その代わり使用者は「リスク」とみなされ、システムへのアクセスが禁止されるようにな るだろう。ドラッグ中毒者は逸脱した悪人ではなくなり、自己の決定によってリスクの高い集団の一部になった人間とみなされるだろう。すなわち、かれらは雇用と社会参加といそして彼は脚註でこう付け加える。
この論文を書いた後、ドラッグ使用が政治的問題として熱心に議論されるようになった。 しかし、そこで実際に展開されているのは奇妙なほど非政治的な議論であり、ドラッグ使 用の道徳的ジレンマについては誰も明確に述べないままである。政策の主眼も、もっぱら ドラッグ検査を体系化するにはどうしたらよいかということに置かれている。そして論拠 として挙げられるのは、ひたすら「リスク」だけである。すなわち、ドラッグを使用する 人々は自分自身を傷つけているだけではなく、経済にもダメージを与えている、というこ とが論拠とされているのだ。
[1987年、p.85]
[ロジャー・ボーイズ、タイムズ紙、1997 年 12 月 1 日]
保険統計主義とリスク社会
驚くべきことであるが、保険統計主義の刑事司法にかんするアカデミズムの言説は、「リスク社会」の特徴にかんする実り豊かな社会学的研究 [Beck, 1992; Giddens, 1991] と無関係に展開されて きた。この指摘は、とりわけジョナサン・サイモンが一九八七年に書いた予言的な論文 「リスク社会の出現」に当てはまる。現在では、その後フィーリーと共同で書かれた新しい刑罰学と 保険統計的な司法にかんする一連の論文 [Feeley and Simon, 1992, 1994; Simon, 1993; Simon and Feeley, 1995] がよく知られるようになったが、その前に書かれた「リスク社会の出現」のほうはもっと幅広い問題領 域を扱っている。ただし、前節でも引用したこの論文は、サブタイトルの「保険・法・国家」 が示すとおり、リスクそのものではなく、リスクへの対処方法について分析したものであった。 アンソニー・ギデンズにとって、リスク社会という概念は、後期近代におけるリスクの特徴 や、リスクへの個人や集団の反応として発達した「計算的な態度」と深く結びついたものである。
高度近代 (ハイモダン) の「世界」で生きることは、暴走する巨大な力に飲み込まれる感覚を抱くことで もある。それは、たんに複雑な社会変化がたえまなく起こっているからだけではなく、こ の変化が人間の期待やコントロールにまったく従わないからでもある。合理的秩序に社会 環境や自然環境を従わせようとする期待は、ますます怪しくなってきた・・・。 神の摂理という考え方――この世の事物の性質を理解することで、人類はもっと安全で実りある生活へと導かれるという考え方——は、前近代社会における「運命」という概念 の名残である。運命という概念にはどこか陰鬱なところがあり、そこには出来事の流れは あらかじめ定められているという意味が含まれている。近代社会の状況においても、運命したい。 ここで私は、犯罪と逸脱の領域において、リスクという概念が根本的にどのような意味を もっているのかを議論したい。また個人や制度、あるいは刑事司法制度において、この概念が どのようにして「計算的」あるいは「保険統計的」な態度を生むことになったのかも明らかに
という伝統的な概念は生き残っている。しかしそれは、リスクが生活の基本的な要素になるだろうという見通しとは、多くの面で相容れるものではない。というのも、リスクをリ スクとして受け入れるということは、・・・私たちの生活が、いかなる意味でもあらかじめ定 められたコースをたどるものではなく、すべて偶然の出来事に左右されるものであると認 めることだからである。この意味において、ウルリッヒ・ベックが近代を「リスク社会」 として描きだしたのはまったく正しいと思われる。この用語は、近代社会の生活がもたら した新たな危険に人類が直面しなければならないということを意味するだけではない。 「リスク社会」に生きるということは、良くも悪くも開かれた可能性をもつ行為にたいし て、人間があくまで計算的な態度をとることも意味している。個人的な次元であろうと世 界的な次元であろうと、私たちが現代の社会生活でつねに直面しているのは、そうした問題である。[1991年、p.28]
ここで私は、犯罪と逸脱の領域において、リスクという概念が根本的にどのような意味を もっているのかを議論したい。また個人や制度、あるいは刑事司法制度において、この概念が どのようにして「計算的」あるいは「保険統計的」な態度を生むことになったのかも明らかにしたい。
参照
ジョック・ヤング著
青木秀男、伊藤泰郎、岸政彦、村澤眞保呂 翻訳
『 排除型社会 ー 後期近代における犯罪・雇用・差異 ー 』
発行 洛北出版
2007年3月10日