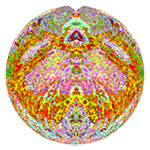谷行人はすべてを語った
大澤真幸
A. 互酬 (贈与と 返礼)
B. 服従と保護 (略取と再分配)
C. 商品交換 (貨幣と商品)
D. Aの 高次元での回復
大澤真幸
柄谷行人はすべてを語った
一語り得なかった「それ」としての「力」
1 すべてを語った
柄谷行人は本書『力と交換様式』を通じて、ついにすべてを語った。読後の私の印象は、 これであった。
もともと柄谷行人の書いたものの魅力は、読者に、「これがすべてではない」という余 剰を感じさせるところにあった。ここにすべては語られていない、すべてが語り得てはい ない、まだ語られていない何かがある。語ることができないこと、語ることの限界を越え る何かがあるのだ。 柄谷行人の初期の文章に、読者はこのようなものを感じてきた。 思考 力の弱さや文章力の欠如が原因ではなく、このような余剰を感じさせる文章を書ける人は ほとんどいない。 柄谷は、そのような稀な書き手の一人であった。そこには、他の誰も到
達できなかった洞察がすでに明示されている。にもかかわらず、 なお 「すべてではない」 と 感じさせるものがある。というより、その不在の余剰へと向けて越境しようとする勢いが、深い洞察を可能なものにしていたのであろう。
ある時期から―交換梯式論の着想を得た世紀の転換点あたりから、柄谷行人は書 態度を変更した。意識的なものなのか、それとも無意識のうちに自然とそうなったのか、 私にはわからない。 とにかく、読む者(私)としては、そのような態度の変更を感じた。 ポジティヴ 「すべてではない」と感じさせる余剰への志向をあえて断念し、まずは積極的に語りうる ことを語ること。すでに初期の仕事を通じて誰も到達していないところまでの洞察を得て いるので、書く態度のこのような変更は、それはそれでまた、柄谷の著作に、これまでに なかった美点や魅力を与えることになった。議論に、全体性と明晰な体系性が与えられた のだ。態度の変更の成果こそが、 次の四つの交換様式によって世界史の構造を説明する理 論であった。
柄谷行人はすべてを語った
大澤真幸
A. 互酬 (贈与と 返礼)
B. 服従と保護 (略取と再分配)
C. 商品交換 (貨幣と商品)
D. Aの 高次元での回復
そして、このたびの『力と交換様式』。 柄谷行人は、「すべてではない」と感じさせたそ の余剰に再び向かった。しかも、今度は、消極的・否定的に「すべてではない」 を示唆し ているだけではない。 「それ」について、ついに積極的に書いたのだ。だから柄谷は今や、 余すことなくすべてを語ったことになる。そのように私には読める。この本は、語り得な いこと、本来は語ることが不可能なことが書かれているという不穏な魅力を発している。 「すべてではない」を感じさせていた「それ」、ほんとうは見てはならない「それ」語る ことが不可能であるはずの「それ」とは何か。それこそが、本書で言うところの「力」、 観念的・霊的な「力」である。
2史的唯物論との対比で
マルクス主義の標準的な理論では、社会構成体(社会システム)の歴史は、建築のメタ ファーによって考えられてきた。土台が経済的なもので、それは生産様式である。上部構 造は政治的観念的なものである。この理論によれば、歴史の決定要因は、もちろん土台 の経済的なもの(生産様式)だということになる。しかし、これに対しては、昔から異論が出されてきた。人間の行動は経済的なベースによって受動的に規定されているだけでは ない、逆に宗教のような観念的上部構造が経済的ベースに対して能動的な「力」を発揮す ることもある、と。 マックス・ヴェーバーも、エミール・デュルケームも、そしてフロイ も、マルクス主義の理論へのこうした反論として読むことができる。
下 だが、観念的上部構造が、経済的ベースからまったく自由に能動性を発揮し、経済的ベ ースを規定しているとする見方も説得力がない。そのため、観念的上部構造は、経済的ベ ースから相対的に自律している、などという曖昧な主張がなされてきた。要するに、どっ ちもどっち、というような論争状況になっていたのだ。
すべてを語った 大澤真幸
それに対して、柄谷は、社会構成体の歴史が経済的ベースによって決定されるという基
木の構図を退けることなく、ここに根本的な変更を加える。経済的ベースは、生産様式で 様式である、と。先ほど述べたように、交換様式には四つのタイプがある。こ ここまでは、『世界史の構造』を代表とする以前の著書の中で、 柄谷が確保してきた論点で ある。その上で、本書『力と交換様式』において付け加えられたのは、上部構造にあると 論者たちが見した観念的な「力」は、実は経済的下部構造、つまり交換様式から来る、 とする論点である。交換様式が四つあるので、「力」もまた四種類になる。観念的な「力」が、経済的下部構造=交換様式に直接由来するのであれば、観念的上部構造が究極の規定 要因なのか、経済的ペースが究極の規定要因なのか、という不毛な論争は、疑似問題とし て退けることができる。だが、「力」とは何か。 様式
二力と交換 力
1Aと
本書『力と交換様式』は、序論を別にすると、四部で構成されている。第三部までは、
史的唯物論の「生産様式の段階」にそって展開されている。すなわち、第一部(「交換か ら来る『力』」で、「アジア的」段階が、第二部(「世界史の構造と『力』」)で、古典古代社 会と封建的社会が、 そして第三部 (「資本主義の科学」)では、近代ブルジョワ社会が論じ られる。第二部と第三部は、ヨーロッパの歴史が中心的な話題となる。四つの「力」が基 本的に何であるかは、最も長い第一部の中で示されている。第一部の叙述を少しだけ編集 しながら、まずは「力」の概要を示しておこう。
「力」の原型と見なしうるのは、交換様式Aに由来する力である。この「力」が何である かを把握する ことができれば、他のタイプの「力」の理解は容易になる。
・えば、さまざまな社会の互酬交換を検討し、贈り物に関して、それを与 また受け取る義務があることに気づいた。 何かが贈与交換を強いているのだ。その何 かは物に付着した霊である、とモースは考えた。ニュージーランドの原住民、マオリ族は、 この霊をハウと呼ぶ。 モースのこの考えは、レヴィ=ストロースをはじめとする後続の論 者たちに、嘲笑的に批判されてきた。それは原住民の迷信を追認しているだけで、科学的説 明にはなっていない、というわけだ。だが、「霊」を斥けた「いかにも科学的」と見える説 では、交換において人間の欲望や意志に反して働いている「力」を見ないことになる。 交換様式Aにともなう 「力」は、モースが見出した霊的な力を肯定的に引き継いだもの である。だが、こういう概念を認めることは非科学的ではないか。そんなことはない。柄 谷は実に巧みな類によって、この点を納得させてくれる。一七世紀に、ニュートンは 万有引力」の概念を導入した。 遠隔的な作用である引力はしかし、オカルト的なもので あるとして、ライプニッツ等に激しく批判された。だが、いかに謎めいており、説明不能 だとしても、実際に「引力」が働くことを認める者たちが結局、近代科学をもたらしたこ と、今日のわれわれは知っている。同じことは、贈与を強いる霊的な「力」についても 言える。 まずはそれがあることを認めることから始めないとならない。
交換様式A(贈与交換)は、人類の定住化とともに始まった。どうして定住がAを強いる ことになるのか。この問いに柄が与えた論理はきわめて独創的かつ重要なので、後で解説 する(本節4)。ともかくここで、交換は、各人の意志を越えた「霊」の力によって成り立 つ。交換様式Aが支配的な社会の典型は、氏族社会やその拡大としての首長制社会である。
2Bと力
交換様式Bにおける「力」とは、もちろん、主権者や支配者が臣民に対して行使する 「力」のことを指しているのだが、重要なことは、この「力」が交換によってもたらされ ているということを見極めることである。臣民は、主権者に隷従する。 その隷従はしかも 自発的なものである。臣民が主権者に、(臣民に)命令する権利を与えているのだ。その 代わり主権者は、臣民の要求に応じる義務を課される。要するに、服従と保護とが交換さ れているのである。Bと「力」の間のこのような関係を最初に理論化したのは本書の 中で繰り返し強調されているが、ホッブズである。ホッブズの言う「契約」とは、 人々が自分たちの自然権を一人の人物に譲渡し、「リヴァイアサン」(毎獣)に喩えられた その一人の人物は、人々を保護する義務を負うことだ。
A「力」の関係を納得していれば、 Bの「力」についてのこうした説明を受け入れる のはそれほど困難ではない。BはAと基本的な点で類似しているからだ。Aの互酬性が、 垂直化すればBになる。Aの場合も「力」が発生しているのだから、その度にミクロには 非対称性(垂直性)が生じているのだが、その非対称性は相互的なものなので、関係は全
体としては水平的である。それに対して、特定の一点が特権的な中心と 固定さ れれば、垂直的な交換としてのBとなる。
なり、非対称性が い。国家はBに基づいている。しかし氏族社会の けではない。Aが、Bが支配的になることに抵抗するからである。互酬的な贈与を強いる
だが、Aが支配的な社会 からBが支配的な社会へのスムーズな移行が生ずるわけではな ような状態から 国家がすぐに出現したわ
すべてを語った 大澤真幸
「力」が相互的に働くと、特権的な固定的中心が生まれないのだ。氏族社会、部族社会は、
もちろん国家以前の社会だ。 再分配を仕切り、調整する首長が出現したとき、ここに国家 の芽を認めることができるが、まだ交換様式Bが支配的になったとはいえない。 首長が王になったときはじめて、Aとは明確に異なった交換様式Bが確立したと見なしうる。 Bが確立されるためには、抑圧されなくてはならない。 その抑圧をもたらすのは、 人々の自発的な隷属化である。国家の成立にとって必要なのは、ただの奴隷ではなく、「自発的に服従する奴隷」だが、それこそが臣民 subject である。 彼らが積極的に服従す るのは、その方が彼らにとっても得だから保護してもらえるから)である。国家において、 王の支配を補助するスタッフも、「自発的に服従する奴隷」である。 それが官僚だ。軍 もまた、自発的に服従している(武官)。
3Cと力
交換様式Cは、實は、「アジア的」段階では、眞に自律的なものとしては確立しない。 BとともにC(商品交換)は共同体と共同体の間の交換として始まるのだが、しかし、「ア ジア的」な段階においては、Cは、基本的にBに寄生している状況を脱することはない。 Cが支配的になるのは、近代資本主義(産業資本主義)の段階だ。ゆえに、Cに対応する
「力」については次節で説明した方がよいのだが、分かりやすさを優先して、ここでまず 概要を述べておく。
基本的なことを言えば、Cに由来する観念的・靈的な「力」は、マルクスが『資本論』 で、商品物神・貨幣 物神等と呼んでいる「物神」がもつ力と同じものである。ただし、 「神」を「比喩としてではなく、文字通りのこととして受け取らなくてはならない。普通は、商品 と人間の関係が物と マルクスの「物神」 しまうと、ポイントを 完全に逃すことになる。 意味されていることがらは 価値をもっていること か理解しにくいかもしれない 解説しよう。マルクスは『資本 契約の論理と同じように説明して いる。貨幣(リヴァイアサン)は商品たちの社会契約の産物だ。ということは、物同士の ている、というこ
物神等は「物象化」の一種として解釈されてきた。物化とは、人間 物との関係に疎外されて現れている、ということだが、 柄谷によれば、 はこれとはまったく逆の事態であり、「物象化」の現象として捉えて 価値貨幣によって測られる と、なぜこれが「力」に関わっているの ことをもとに――ただしそれを単純化して 品の集合から貨幣が成立する仕組みを、ホッブズの社会
「商品物神」という語で、さまざまな物が商品として、一般的 そのものなのだが、これだけだ 。 柄谷が述べている 論』で、商関係、貨幣と商品たちの関係だけみると、交換様式Bと同じことが起き とになる。 商品たちは貨幣に自発的に隷属し、その代わり、貨幣の保護を 受ける(交換可価値を与えられる)のだ。 ならば、 交換様式とその「力」はBの一種かと言ったらそうではない。 Bの形式をと っているのはあくまで物同士の関係である。人間の方はむしろ、Bの「支配/服従」の関係から自由だと思っている(たとえば王のカリスマ性など、もうまったく信じていない)。に もかかわらず、貨幣や商品の所有者として市場に参入し、そこで交換している限り、意識 に反して、その人の行動は、B的な支配/服従の関係の中にいるのと同じことになる。こ 交換様式に対応する「力」の概要だ。 商品物神・貨幣物神は、さらに資本物神へと 発展する等、CにはBと対応づけられない展開があるのだが、それについては後述する。 歴史に即して、Cの展開を見ておく。 先ほど述べたように、CはBと同時に始まる。ど んな交換も信用なくしてありえず、信用を形成するのは贈与である。その意味で、Cの根 底にはAがある。貨幣には諸物と交換しうる「力」がある。その「力」を付与するのは国 家である……と言いたくなるがそうではない。貨幣物神だ。とはいえ、国家の保証がなく では、貨幣は貨幣として機能しない。その意味では、貨幣経済は国家の下にある。
古代国家にとって重要なのは、国家によって主導された遠隔地との間の交易である。 かし、この交易の拡大を、単純にCの拡大と見なすことはできない。遠隔地交易の目的は、 「王の威信」の拡大にあり、交易に従事した国家官僚(商人ではないことに注意)を突き動 かしたのは、利潤動機ではなく身分動機だった。要するに、古代世界での交易の拡大は、 Cの発展よりむしろ、Bの発展に貢献した。 こうして都市国家を超えた領域国家が、さらそれをも超えた帝国が出現した。帝国は、諸民族の自発的な服従によって成り立ち(つ まりB)、世界交易 (C)をも実現したが、モンゴル帝国のような巨大な帝国でも、資本主 義経済に向かわなかったのは、世界帝国(B)が、Cの発展を抑えたからである。 帝国には、神格化された王、つまり皇帝が
君臨する。皇帝は、王たちを臣下として従え るのだから、王とは同格ではありえない。ということは、皇帝の背後にいる神もまた、そ れまでの神々を超越する神になっているということでもある。世界帝国に対応する神は世 界神であり、その宗教は世界宗教である。 世界宗教は、この後で説明する普遍宗教とは異 なっている。
4 Aの高次元での回帰としてのD
柄谷が最も重要視している交換様式はDである。だがDは、他の三つから独立した独自 の交換様式ではない。Dは、交換様式Aの回帰、しかもそれが「高次元」で回帰したもの だ。「高次元」での回帰とはどういうことなのか。人類が定住して以降、Aはずっと存在 している。しかし、BやCを補完したり、支えたりする要素として存在しているときには、 Aは、高次元で回したとは言えない。「高次元」で回帰するとは、BCが発展した後、BやCに対抗する要素としてAが立ち帰ってくることである。なぜ、Aは回帰してくるのか。 この問いに答えるためには、どうしても、交換様式Aとセットになっているあの霊的な 「力」がどうして生ずるのか、人に贈与を強いる「力」は何に由来するのかを問わざるを えない。この点に本書が与えている説明を、そのまま紹介しよう。
定住とともに贈与交換 (A)が始まる、と述べた。どうしてなのか。定住以前の初期の 人類社会は、 少人数 (五〇人程度)によって構成された遊動民の社会である。こういう社 会には、贈与など必要ない。なぜなら、物は――たとえば狩猟の獲物は、直接に 共同寄託され、分有されるからである。これは、贈与があまりに純粋すぎて、贈与として 成り立たない状態(初めから皆のものとして与えられているので、誰から誰へと贈るというこ とが意味をなさない状態)だと言うこともできるだろう。
柄谷は、原初的な遊動民は、「無機質」の状態にある、と言う。「無機質」の状態とは、 要するに、シンプルな状態ということだが、肝心なことは、そこには、最も原初的な意味 での平等と自由があるということだ。平等というのは、今述べたように、物がすべて直接 共同寄託されているからだ。また自由であるというのは、たとえば人間関係のトラブルな ど嫌なことがあれば、いくらでも移動することが(つまり外に出ていくことができるからである 。この「無機質」の状態は、原遊動性(U)と呼ばれる。
だが、定住は、社会に「有機的」な状態をもたらす。つまり社会を複雑化する。原遊動 性にはあった原初的な自由=平等が失われる危険に見舞われる。ここで柄谷は、人間には、
「無機質に戻ろうとする」 本源的な欲動がある、と仮定する。この欲動こそ、フロイトが 「死の欲動」と呼んだものである、と。このような欲動があるとして、社会が「有機的」な 状態へと向かうとしたら、何が起きるか。まずは、他者に向けられた攻撃欲動が奔出する だろうが、それをさらに抑えようとすれば、他者への譲渡=贈与を迫る「反復強迫」が現れ るのではないか。社会に孕まれた複雑性(たとえば格差)を解消しようと、人々は譲渡=贈 与へと反復的に駆り立てられるのだ。この反復強迫が「霊」の命令というかたちで出現する。 このように、柄谷によれば、もともと交換様式Aは、原遊動性へと回帰しようとする欲 動の結果として生まれた。だがAから、BやCへと発展すると、そこに出現する社会の状
熊は、原遊動性とはほど遠いものになる 。それゆえ、原遊動性への回帰は、BやCが発達 した後には、直接のAとは異なったかたちで現れる。それが交換様式である。普宗教
は「帝国を支える一神教」である世界宗教とは異なる普遍宗教はまさにそのような意味の(高次元で回帰したA)の出現である。