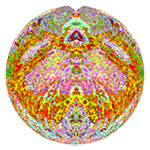ナンバーワンからオンリーワンへ
第1章 「ナンバー・ワン」の強迫観念
人生とは、だれにとっても、たえまなく競い合いをつづけていくものになっている。 めざまし時計がけたたましい音をたてる瞬間からふたたび眠りにつくまで、よちよち歩きの子どものころから死ぬその日まで、 他人をうちまかそうとあわただしくしのぎをけずる。これが、職場においても、学校においても、また外 で遊ぶときでも、家に帰ってからでも、われわれがとっている姿なのである。これが、アメリカの生活に ふつうにみられる特徴なのである。
われわれがあまりにも競争に熱中しすぎてしまうために、競争のほうは、たやすく監視の目をかいくおおぐってしまう。かつてウォーカー・パーシーが述べたように、魚は、水の本質について考えたりはしない が、「水がない状態を想像することができないので、その存在について熟考することもできないので ある」。生活のためにものを考えたり、文章を書いたりする人びとでさえ、この問題にほとんど目をむけ ないのはおどろくばかりである。たとえば、ここ五〇年のあいだに、競争という概念そのものを解明した 本は一冊も書かれていないし、人間の生活のありとあらゆる場面においてこの概念がどのような意味あい でもちいられるのかについてふれたものもない。ここでは、今日のスポーツの現状について嘆いてみたり、 ビジネスで勝利をおさめる方法について語ったり、ゲームの実験を行って問題点をさがしだし、統計的な 操作をほどこそうなどというつもりはない。 そんなものは、いつでも新聞の紙面で目にすることができる。
わたしが行いたいと思っているのは、他人をうちまかそうとする行為が実際どのような意味をもつのかと いうことに目をむけ、ある人びとが勝利するためにはべつの人びとが敗北しなければならないような仕組 みがどのようなものなのかについて、目をこらして考察してみることである。
この種の分析がとうの昔に行われていなければならないものだということになると、それは、ほかの国 よりもこの国においてこそ急を要するはずである。 それぞれの文化は、程度こそことなるが、いろいろな 意味で競争に依存している。その程度におうじて、経済システム、学校教育、レクリエーションが組織化 されるのである。一方の極には、競争がまったく存在しないままに機能している社会がある。 そして、も う一方の極には、アメリカの社会が存在しているのである。 社会心理学者のエリオット・アロンソンの文 章から引用してみよう。
自分のチームが負けたあと泣きだしてしまうリトル・リーグの野球選手から、フットボールのスタジアムで 「おれたちはナンバーワンだぞ」と互いにたたえあう大学生まで、また、はじめて戦争に負ける大統領にな りたくないというおさだまりの願望をいだいたために判断をあやまったことがはっきりしているリンドン・ ジョンソンから、算数の試験でよい成績をおさめたことを鼻にかけて同級生を軽蔑する小学校の三年生まで、 (
勝利にかんしてはおどろくほど文化的な強迫観念をあらわにするのである。 ( ほかの研究者も、おなじような言い方をしている。「わが国においては、競争は、ほとんど宗教そのも のだ」とある観察者はいっている。また、競争は「アメリカ文化の常備薬だ」、とべつの観察者は述べて いる。「競争に反対すれば、反アメリカ的だとみなされる」、とさらにもうひとりの観察者が書きとめてい
る。
これは、競争がアメリカだけにみられるものだという意味ではない。本書のなかで示しておいたさまざ まな例は、おそらくほかの国でも読者がよくお目にかかるものだろう。だが、ほかの国ではごくふつうに みられるものでも、アメリカでは誇張されてしまい、こっけいなものになってしまうことがおおいのであ る。それは、競争の行動がひろく行きわたっていること、競争の行動を夢中になって行うことの両方から うかがえる。アメリカの経済システムは、競争にもとづいている。 学校教育も、一年生のころから、他人 に勝つだけでなく、他人を自分の成功をはばむ障害物とみなすように訓練するのである。余暇の時間にも、 きわめて組織的に行われるゲームが目白押しであり、一方の個人ないしはチームが、もう一方の個人ない しはチームをうちまかさなければならないのである。家族のあいだでもせりあいが存在しており、もの静 かなうちにも、命がけの闘争が行われ、賛同は貴重な商品としてあつかわれ、愛は勝利のトロフィーに なってしまう。
われわれは、競争行動に熱中するだけでなく、ほかのものも、ほとんどすべてを競い合いにかえてしま うのである。集団が発揮する創造力も、勝者と敗者をつくりだすあらたな方法の開発にかかりきりになっ ているように思われる。もっと生産性をあげるためには、職場の同僚と闘うだけでは十分ではない。もっ とも忠実な従業員というタイトルをかけて競争しなければならないのである。ほかの会社で働いている人 たちとつきあうときに考えつくのはただひとつ、競争というゲームでやつらをうちまかすようつとめるこ とである。 このようなことから逃れようと思って、たとえばダンスをしに外出したとしても、そこでもま 競い合いにまきこまれていることを思い知らされてしまう。われわれの生活のどこをとってみても、あ まりにもありふれたものであるために、あるいは、ぎゃくにあまりにも重要なものであるために、自分を 他人と比較して評価するよう強制されないものなどないのである。競い合いがはっきりとしたかたちでは生じていない場合でも、世の中のことについては競争という意味で解釈しがちなのである。ちょっとした 実例をあげてみよう。 数年前、『ニューヨーク・タイムズ・マガジン」は、プラシード・ドミンゴのプロ フォールを特集欄に掲載して、 「世界一のテノール歌手の座をかけてルチアーノ・パパロッティに挑戦し てきたが、おおくの人がいうように、ドミンゴが勝利をおさめた」と宣言した。オペラもまた、だれがナ ンバーワンの歌手なのかを考えないと楽しめなくなってしまっているのだ。 このように、「勝利することがすべてなのではなく、唯一のものなのだ」というヴィンス・ロンバル ディの有名なことばは、あるフットボールのコーチの熱狂ぶりを示しているだけではなく、わが国全体の (7)
文化的に描きだしたものだと理解されるべきなのである。われわれの生活も、「もっとよくならな ければならないということに影響されるだけでなく、「もっとよくならなければならないということに もとづいて組織化されるのである。 仕事をし、子供たちを教育し、週末に休みをとることが、だれかが負 わなければならない闘争の状況のなかで生じるのだという時点にすでに行きついてしまっているようにみ える。したがって、仕事や教育を行うにしてもべつのやり方があるかもしれないということは、想像しに
くくなっている。また、競争しているのだということを十分に自覚していたとしても、はじめから競争に かわるものを思いつくのはむずかしいだろう。たいていの場合は、ただ「これがあたりまえのやり方なの だ」とうけいれるだけなのである。 現代においては、ビジネスにおける競争にもっとも顕著にあらわれているように、こうした問題は、ま きに時代を象徴するものになっている。書店には、市場で勝者になるための手引きがあふれているが、そ れはおもにここ数年のあいだにワシントンからまきちらされた美辞麗句のおかげである。実際、あとさ きも考えずに戦争があおられてしまったために、選挙によって選ばれた代表者から私企業に、また理論上は、すべての市民に責任をもつと想定されている者から、せいぜい利益をあげることに固執するごくわず かの人びとだけに責任をもつ者に権力が移行する結果をまねいてしまっている。(すべての法人資本の半 分は、人口の一%によって所有されているが、それにたいして、すべての家族のうち八一%は、まったく 財産を所有していない)。だが、これから数年後に、企業が成功する秘訣なるものがいまほど幅をきかせ なくなったとしても、また公務員が自分たちのことを私企業の応援団長だとみなさなくなったとしても、 わが国の経済システムは、根本的に競争にもとづいているのであり、この問題の究明も、その点にかかわ るものでありつづけるだろう。さらに、本書では、実業界のたくらみにとどまらず、それをはるかにこえ たものに関心をよせている。競争は、われわれの生活にふかく染みこんでおり、つねにつきまとっていく のである。競争がどのような影響をおよぼすのかを、いっそう目をこらしてみすえるべきなのである。
この問題をもっと正確に定式化することからはじめよう。 わたしは、いわゆる構造的な競争と意図的な とを区別したほうがいいと思う。前者は状況について語ったものであり、後者は態度について語った 。構造的な競争は、 勝利 敗北の枠組みをとりあつかうもので、外在的なものである。それに 意図的な競争は、内在的なもので、ナンバー・ワンになりたいと思う個人の側の願望にかんす るものである。 が構造的な競争にあたるといえるのは、互いに排他的な目標達成 (MEGAと略記)とわたし
「ナンバー・ワン」の強迫観念
ものである
たいして、
ある行動
第1章
が名づけるものを特徴としているからである。簡単にいえば、これは、自分が成功するためには相手が失 敗しなければならないということである。否定的な意味においてであるが、われわれの運命は結びついては、すべての市民に責任をもつと想定されている者から、せいぜい利益をあげることに固執するごくわず かの人びとだけに責任をもつ者に権力が移行する結果をまねいてしまっている。(すべての法人資本の半 分は、人口の一%によって所有されているが、それにたいして、すべての家族のうち八一%は、まったく 財産を所有していない)。だが、これから数年後に、企業が成功する秘訣なるものがいまほど幅をきかせ なくなったとしても、また公務員が自分たちのことを私企業の応援団長だとみなさなくなったとしても、 わが国の経済システムは、根本的に競争にもとづいているのであり、この問題の究明も、その点にかかわ るものでありつづけるだろう。さらに、本書では、実業界のたくらみにとどまらず、それをはるかにこえ たものに関心をよせている。競争は、われわれの生活にふかく染みこんでおり、つねにつきまとっていく のである。競争がどのような影響をおよぼすのかを、いっそう目をこらしてみすえるべきなのである。
この問題をもっと正確に定式化することからはじめよう。 わたしは、いわゆる構造的な競争と意図的な とを区別したほうがいいと思う。前者は状況について語ったものであり、後者は態度について語った 。構造的な競争は、 勝利 敗北の枠組みをとりあつかうもので、外在的なものである。それに 意図的な競争は、内在的なもので、ナンバー・ワンになりたいと思う個人の側の願望にかんす るものである。 が構造的な競争にあたるといえるのは、互いに排他的な目標達成 (MEGAと略記)とわたし
ものである
たいして、
ある行動
が名づけるものを特徴としているからである。簡単にいえば、これは、自分が成功するためには相手が失 敗しなければならないということである。否定的な意味においてであるが、われわれの運命は結びついて